ヘルスケアコラム
否定的な考え方を修正して心身の症状の軽減をめざす
人の気分は、現実の物事ではなくとらえ方により左右される
「認知療法」とは、アメリカの精神科医アーロン・ベックにより考案された精神療法です。何らかの出来事により不安や抑うつなどの精神症状や身体症状が起きた場合、認知療法では受け止め方や考え方のパターンに注目します。誤った考え方や視覚的イメージ(認知体系)を修正しながら心やからだの症状を軽減させ、最終的には自分自身でコントロールできることを治療目標とします。
「人の気分は、現実の物事や状況によるのではなく、とらえ方により左右される」が認知療法の基本的な考え方です。
たとえば、仕事で大きなミスをして、上司から怒られた状況を想定してみましょう。ひどく落ち込み自信をなくして後悔ばかりしている人もいますし、この苦い経験を糧(かて)として前向きに自己成長する人もいます。前者はストレスに弱くすぐに落ち込んでしまう考え方の人で、後者はストレスに強い考え方や感じ方のできる人です。個々の考え方や感じ方の心のくせを認知療法では「自動思考」と呼びます。
「人の気分は、現実の物事や状況によるのではなく、とらえ方により左右される」が認知療法の基本的な考え方です。
たとえば、仕事で大きなミスをして、上司から怒られた状況を想定してみましょう。ひどく落ち込み自信をなくして後悔ばかりしている人もいますし、この苦い経験を糧(かて)として前向きに自己成長する人もいます。前者はストレスに弱くすぐに落ち込んでしまう考え方の人で、後者はストレスに強い考え方や感じ方のできる人です。個々の考え方や感じ方の心のくせを認知療法では「自動思考」と呼びます。
その人の環境や状況の把握からスタート
認知療法は、その人がどういう環境に置かれているのか、どういう状況にあるのかを把握することから始めます。個人と環境の相互作用を押さえたうえで、その人自身の認知、行動、気分や感情、身体的反応、すなわち個人内の相互作用を二重に見ていくのが認知療法の基本モデルです(図1)。
考えやイメージをネガティブでないものに再構成する方法も
認知療法の技法の一つに「認知再構成法」があります。狭義の認知療法と言われており、過度にネガティブな気分や感情と関連する認知、すなわち考えやイメージを把握して、そうでない認知を再構成する方法です。
具体的には出来事、気分、自動思考、別の考え、結果を記録表に書き込みながら、認知のゆがみを体験的に修正していきます。それぞれが当初何%であったかも記入します。
たとえば、妻と口論してイライラしている状態を考えてみましょう。イライラが80%とします。自分が正しいという自動思考が80%ですが、別の考え方も記入してみます。自分も少し言いすぎてしまった(60%)と違った見方をすると、その結果気が楽になりイライラも60%に減少するかもしれません。問題となる自動思考の確信度が減り、別の考えの割合が高くなれば、治療効果があったと検証されます。専門のカウンセラーと記録表を一緒に作成していきながら自己成長を促していくのが治療のポイントです。
具体的には出来事、気分、自動思考、別の考え、結果を記録表に書き込みながら、認知のゆがみを体験的に修正していきます。それぞれが当初何%であったかも記入します。
たとえば、妻と口論してイライラしている状態を考えてみましょう。イライラが80%とします。自分が正しいという自動思考が80%ですが、別の考え方も記入してみます。自分も少し言いすぎてしまった(60%)と違った見方をすると、その結果気が楽になりイライラも60%に減少するかもしれません。問題となる自動思考の確信度が減り、別の考えの割合が高くなれば、治療効果があったと検証されます。専門のカウンセラーと記録表を一緒に作成していきながら自己成長を促していくのが治療のポイントです。
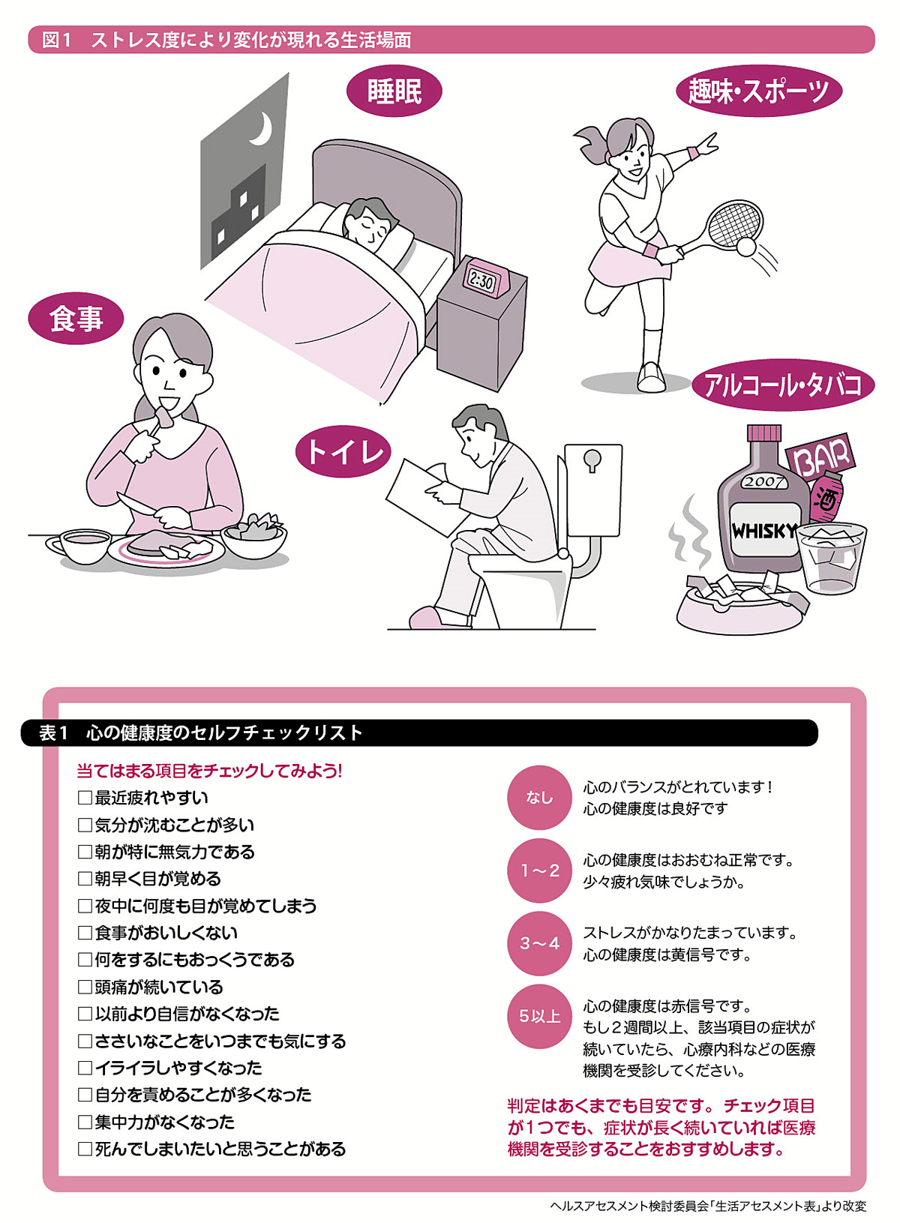
【引用・参考文献】
総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画
総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

 お問い合わせ
お問い合わせ

