先生の声
登山前に注意!知っておくべき「高山病」とは(その1)
初めての登山!頂上に登った時のことやみんなで楽しく登っていることを想像して、心弾ませている人も多いと思います。しかし、初めての登山にはたくさんの危険が潜んでいます。その代表的なものの一つが「高山病」。せっかくの楽しい登山が台無しにならないよう、また万が一病気になってしまったときにすぐに対処できるよう、最低限の知識を身につけて登山に臨みましょう。
どうして「高山病」が起こるの?
「高山病」とは高い山等に登った際に、酸素が薄くなった空気を吸う事で生じる様々な症状をまとめたものです。海面の高さでも、高い山の上でも空気中の酸素濃度はおよそ21%ですが、高いところでは気圧が低くなり空気は薄くなります。海抜5500mの山に登ると大気圧は海面の高さのおよそ半分になり、その21%を占める酸素も半分に薄まってしまいます。酸素呼吸をする生き物は細胞の中で酸素を使って大きなエネルギーを生み出しています。その大切な酸素が不足すると生命の危機にも繋がるトラブルが起きてしまうのです。
ちなみに肺で吸った酸素を体中に届けているのはヒトの場合、血液の中の赤血球に入っているヘモグロビンという鉄を含んだ物質です。高い山に上った時と同様にお母さんのお腹の中にいる胎児や、水中に長時間潜むワニも酸素の少ない環境におり、それぞれ特殊なヘモグロビンを持っています。
胎児はお母さんとは血液型が違う可能性のある別個の生命で、胎盤によって互いの血液が直接混ざり合わない様に隔てられています。胎盤を通じて少ない酸素を受け取れる様に胎児はヘモグロビンFという大人のヘモグロビンAよりも酸素と結びつきやすいヘモグロビンを持っています。ただし出生後3−5日でヘモグロビンFは急速に破壊され、ビリルビンという物質になり新生児黄疸の原因となります。6ヶ月から1年でヘモグロビンFはヘモグロビン全体の1%以下に減るので、赤ちゃんが高山病に強いわけではありません。くれぐれもご注意ください。
ワニの場合は潜水用の副肺を持っている、筋肉に酸素を溜めている、脾臓に酸素を溜めている、ヒトよりも酸素を運ぶ能力が高いヘモグロビンを持っているため1時間以上潜水できるのだそうです。酸素を使ってエネルギーを作り出すと二酸化炭素ができます。二酸化炭素は水に溶けると水素イオンと炭酸水素イオンに分かれて存在します。ヒトのヘモグロビンは水素イオンが多くなると酸素を離して細胞に提供し易くなります。エネルギーを沢山使って二酸化炭素が増えたところにどんどん酸素を供給できる仕組みです。ヒトのヘモグロビンは4つの酸素を結びつきますが提供できる酸素は1つだけです。ところがワニでは2つから3つの酸素を提供できるそうです。これはワニのヘモグロビンが水素イオンばかりでなくもう一方の炭酸水素イオンの影響も受けて酸素を提供できるからです。ワニのヘモグロビンの研究は酸素不足で苦しむ病気の治療やスポーツに大きな影響を与えそうですね。
ちなみに肺で吸った酸素を体中に届けているのはヒトの場合、血液の中の赤血球に入っているヘモグロビンという鉄を含んだ物質です。高い山に上った時と同様にお母さんのお腹の中にいる胎児や、水中に長時間潜むワニも酸素の少ない環境におり、それぞれ特殊なヘモグロビンを持っています。
胎児はお母さんとは血液型が違う可能性のある別個の生命で、胎盤によって互いの血液が直接混ざり合わない様に隔てられています。胎盤を通じて少ない酸素を受け取れる様に胎児はヘモグロビンFという大人のヘモグロビンAよりも酸素と結びつきやすいヘモグロビンを持っています。ただし出生後3−5日でヘモグロビンFは急速に破壊され、ビリルビンという物質になり新生児黄疸の原因となります。6ヶ月から1年でヘモグロビンFはヘモグロビン全体の1%以下に減るので、赤ちゃんが高山病に強いわけではありません。くれぐれもご注意ください。
ワニの場合は潜水用の副肺を持っている、筋肉に酸素を溜めている、脾臓に酸素を溜めている、ヒトよりも酸素を運ぶ能力が高いヘモグロビンを持っているため1時間以上潜水できるのだそうです。酸素を使ってエネルギーを作り出すと二酸化炭素ができます。二酸化炭素は水に溶けると水素イオンと炭酸水素イオンに分かれて存在します。ヒトのヘモグロビンは水素イオンが多くなると酸素を離して細胞に提供し易くなります。エネルギーを沢山使って二酸化炭素が増えたところにどんどん酸素を供給できる仕組みです。ヒトのヘモグロビンは4つの酸素を結びつきますが提供できる酸素は1つだけです。ところがワニでは2つから3つの酸素を提供できるそうです。これはワニのヘモグロビンが水素イオンばかりでなくもう一方の炭酸水素イオンの影響も受けて酸素を提供できるからです。ワニのヘモグロビンの研究は酸素不足で苦しむ病気の治療やスポーツに大きな影響を与えそうですね。

執筆者
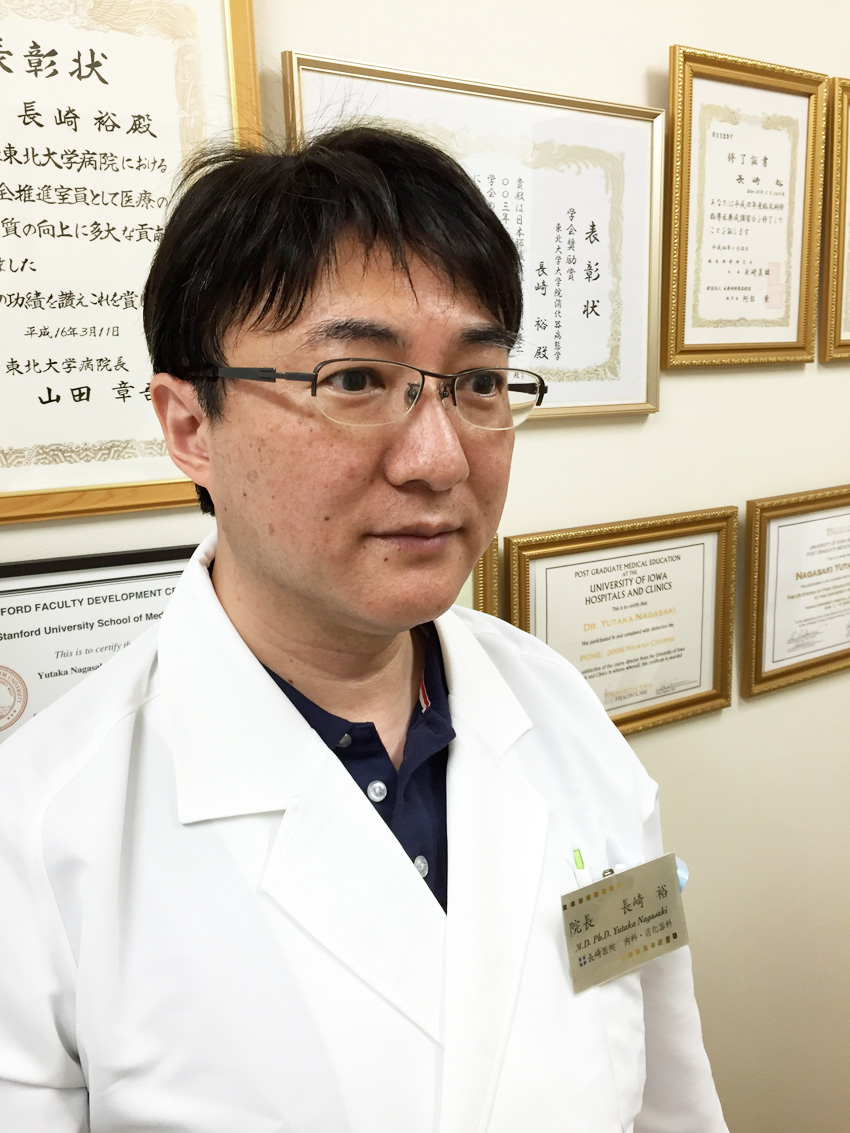
長崎医院
院長 長崎裕
(略歴)
平成3年3月、東北大学医学部卒業
平成v3年6月、山形市立病院済生館 内科研修医
平成5年4月、東北大学医学部第三内科入局(膵グループ)
平成10年4月、福島市大原医療センター消化器科赴任
平成11年4月、東北大学医学部第三内科 消化器内科)医員
平成12年10月、東北大学医学部総合診療部 助手
平成19年4月、東北大学病院総合診療部 講師、医局長、副部長
平成22年3月、東北大学医学部教室員会 委員長平成23年6月、長崎医院 院長
院長 長崎裕
(略歴)
平成3年3月、東北大学医学部卒業
平成v3年6月、山形市立病院済生館 内科研修医
平成5年4月、東北大学医学部第三内科入局(膵グループ)
平成10年4月、福島市大原医療センター消化器科赴任
平成11年4月、東北大学医学部第三内科 消化器内科)医員
平成12年10月、東北大学医学部総合診療部 助手
平成19年4月、東北大学病院総合診療部 講師、医局長、副部長
平成22年3月、東北大学医学部教室員会 委員長平成23年6月、長崎医院 院長

 お問い合わせ
お問い合わせ

