先生の声
登山前に注意!知っておくべき「高山病」とは(その2)
初めての登山!頂上に登った時のことやみんなで楽しく登っていることを想像して、心弾ませている人も多いと思います。しかし、初めての登山にはたくさんの危険が潜んでいます。その代表的なものの一つが「高山病」。せっかくの楽しい登山が台無しにならないよう、また万が一病気になってしまったときにすぐに対処できるよう、最低限の知識を身につけて登山に臨みましょう。
「高山病」の症状って?
高山病の原因は低酸素状態です。概ね標高2500mでは酸素は海面上の73%に薄まります。1日で1800mから2500m以上登れば高山病が出やすくなりますが、1200mでも症状が出る事があります。ちなみに富士山は5合目で2300mです。途中まで車やヘリコプター等を使用して比較的容易に高地に行く事も可能になりましたが、乗り物を使用しても高山病は発症しますから注意が必要です。また、登山の経験が増えても高山病の症状が出なくなる事はないそうです。ただし高山病になりやすい体質かどうか確かめる、高山病の症状を体験し対応方法になれる等を目的としてトレーニングをすることはあるようです。
次に高山病の症状ですが、①山酔い、②高地脳浮腫、③高地肺水腫の3つに分かれます。
① 山酔い:頭痛、倦怠感、吐き気、嘔吐など二日酔いのような症状です。高地についてから6〜12時間後に始まります。「妙に気分が良く感じる」多幸感のために、自分の体調の変化に気付きにくくなる事があります。自覚症状ばかりでなく、呼吸や心拍数が増えていないか、唇や爪の色が紫になっていないか、受け答えが遅くなる、痙攣や意識がもうろうとなるなどの変化にお互い注意してください。
② 高地脳浮腫:倦怠感が強まり考えがまとまらず、ふらふらしてまっすぐ歩けなくなります。踵とつま先を交互に付けて一本橋をわたる様に歩けなくなります。ちなみに高度3000m〜4500mを飛ぶ飛行機では低酸素症が出てから1時間以内に意識を失い、高度5400mでは30分、7500mでは2〜3分とその時間が短くなります。
③ 高地肺水腫:最初動いた後の息切れが強くなります。徐々に休んでいても息切れが出てきます。安静にしても数分以上息切れが続く時には直ちに対応が必要です。
では、低酸素症になると体の中ではどんなことが起きるのでしょうか。低酸素直接引き起こす障害と、それに対する体の適応力のバランスで様々な状態になります。
1)呼吸回数の増加
大気中の酸素が薄くなり血液中の酸素が低下すると呼吸中枢が刺激され呼吸の回数が増えます。しかし呼吸の回数が増えると炭酸ガスは「はく息」の中にどんどん放出され血液がアルカリ性になって呼吸中枢の刺激が抑えられ、呼吸の回数が減り血液中の酸素濃度が上がらなくなります。
2)頭痛、震え、脳浮腫
酸素が薄い状態にもかかわらず呼吸数が十分増えないと血液中の酸素が減り二酸化炭素が増えてしまいます。血液中の二酸化炭素が増えると血管が広がり、脳をめぐる血液の量は増加します。脳は頭蓋骨によって包まれているので血液の量が増えると脳にかかる圧力が増えて頭痛や震え、高地脳浮腫を引き起こすと考えられています。
3)尿量の増加
腎臓はアルカリ性である重炭酸を尿にどんどん排出し、アルカリ性に傾いた血液pHを改善し呼吸回数が多い状態を保とうとします。また高地では手足や体の表面の静脈は収縮し、内蔵等、体の奥を巡る血液量が増えます。血圧が高まったと体が感知して尿量が増えるようにホルモンが調節されます。尿がどんどん出れば血液の酸性−アルカリ性のバランスは高地に適応しますが、体の水分が不足する脱水状態が心配になります。逆に十分尿がでなければ全身がむくんできます。
4)息切れ、肺水腫
大気の酸素がうすくなった時に最も深刻なことは、肺の血管が縮んで細くなることです。肺の血管が狭まり循環が悪くなると肺がむくんで酸素が血液中に取り込まれにくくなる高地肺水腫になってしまいます。
5)脈拍の増加
心臓の筋肉は酸素が少ない状況にも比較的耐えられますが自律神経が刺激を受けて脈拍が多くなります。また先ほどの重炭酸の尿への排出とホルモンの調節で尿量の増加によって血液は濃縮し体を巡る血液量は減ることも脈拍を増加させる原因となります。
6)しびれ、関節痛
これらの症状は一般的な高山病の症状ではありませんが、登山に関連した症状です。その一部には細かい血管が詰まる事が関係しているかもしれません。高地に上った時にも潜水で深いところから急浮上した時のような減圧症を起こし、血液の中に溶けきれなくなった窒素ガスが気泡になって細かい血管に詰まる可能性があります。特に乗り物を利用して急速に高地に移動する時には注意が必要です。
また高地に到着後2時間ほどで酸素を運ぶ能力を高めようと赤血球を増やすホルモンが増えます。スポーツ選手が行う「高地トレーニング」ではこの現象が利用されています。数日~数週で赤血球の数が増えて酸素を運ぶ能力は上がりますが血液は濃くなるため詰まりやすくなります。尿量が増えて脱水になりやすい事も合わせて血管が詰まりやすくなる要素が重なっています。
次に高山病の症状ですが、①山酔い、②高地脳浮腫、③高地肺水腫の3つに分かれます。
① 山酔い:頭痛、倦怠感、吐き気、嘔吐など二日酔いのような症状です。高地についてから6〜12時間後に始まります。「妙に気分が良く感じる」多幸感のために、自分の体調の変化に気付きにくくなる事があります。自覚症状ばかりでなく、呼吸や心拍数が増えていないか、唇や爪の色が紫になっていないか、受け答えが遅くなる、痙攣や意識がもうろうとなるなどの変化にお互い注意してください。
② 高地脳浮腫:倦怠感が強まり考えがまとまらず、ふらふらしてまっすぐ歩けなくなります。踵とつま先を交互に付けて一本橋をわたる様に歩けなくなります。ちなみに高度3000m〜4500mを飛ぶ飛行機では低酸素症が出てから1時間以内に意識を失い、高度5400mでは30分、7500mでは2〜3分とその時間が短くなります。
③ 高地肺水腫:最初動いた後の息切れが強くなります。徐々に休んでいても息切れが出てきます。安静にしても数分以上息切れが続く時には直ちに対応が必要です。
では、低酸素症になると体の中ではどんなことが起きるのでしょうか。低酸素直接引き起こす障害と、それに対する体の適応力のバランスで様々な状態になります。
1)呼吸回数の増加
大気中の酸素が薄くなり血液中の酸素が低下すると呼吸中枢が刺激され呼吸の回数が増えます。しかし呼吸の回数が増えると炭酸ガスは「はく息」の中にどんどん放出され血液がアルカリ性になって呼吸中枢の刺激が抑えられ、呼吸の回数が減り血液中の酸素濃度が上がらなくなります。
2)頭痛、震え、脳浮腫
酸素が薄い状態にもかかわらず呼吸数が十分増えないと血液中の酸素が減り二酸化炭素が増えてしまいます。血液中の二酸化炭素が増えると血管が広がり、脳をめぐる血液の量は増加します。脳は頭蓋骨によって包まれているので血液の量が増えると脳にかかる圧力が増えて頭痛や震え、高地脳浮腫を引き起こすと考えられています。
3)尿量の増加
腎臓はアルカリ性である重炭酸を尿にどんどん排出し、アルカリ性に傾いた血液pHを改善し呼吸回数が多い状態を保とうとします。また高地では手足や体の表面の静脈は収縮し、内蔵等、体の奥を巡る血液量が増えます。血圧が高まったと体が感知して尿量が増えるようにホルモンが調節されます。尿がどんどん出れば血液の酸性−アルカリ性のバランスは高地に適応しますが、体の水分が不足する脱水状態が心配になります。逆に十分尿がでなければ全身がむくんできます。
4)息切れ、肺水腫
大気の酸素がうすくなった時に最も深刻なことは、肺の血管が縮んで細くなることです。肺の血管が狭まり循環が悪くなると肺がむくんで酸素が血液中に取り込まれにくくなる高地肺水腫になってしまいます。
5)脈拍の増加
心臓の筋肉は酸素が少ない状況にも比較的耐えられますが自律神経が刺激を受けて脈拍が多くなります。また先ほどの重炭酸の尿への排出とホルモンの調節で尿量の増加によって血液は濃縮し体を巡る血液量は減ることも脈拍を増加させる原因となります。
6)しびれ、関節痛
これらの症状は一般的な高山病の症状ではありませんが、登山に関連した症状です。その一部には細かい血管が詰まる事が関係しているかもしれません。高地に上った時にも潜水で深いところから急浮上した時のような減圧症を起こし、血液の中に溶けきれなくなった窒素ガスが気泡になって細かい血管に詰まる可能性があります。特に乗り物を利用して急速に高地に移動する時には注意が必要です。
また高地に到着後2時間ほどで酸素を運ぶ能力を高めようと赤血球を増やすホルモンが増えます。スポーツ選手が行う「高地トレーニング」ではこの現象が利用されています。数日~数週で赤血球の数が増えて酸素を運ぶ能力は上がりますが血液は濃くなるため詰まりやすくなります。尿量が増えて脱水になりやすい事も合わせて血管が詰まりやすくなる要素が重なっています。

執筆者
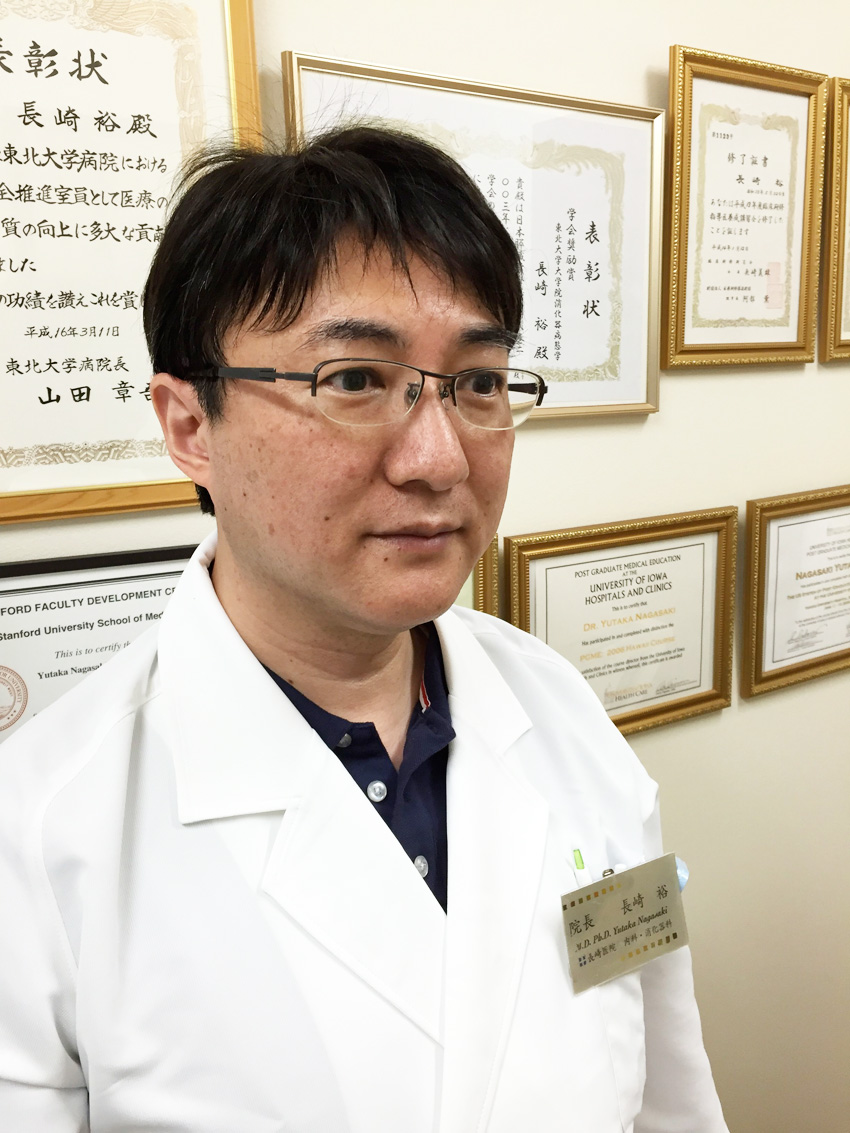
長崎医院
院長 長崎裕
(略歴)
平成3年3月、東北大学医学部卒業
平成v3年6月、山形市立病院済生館 内科研修医
平成5年4月、東北大学医学部第三内科入局(膵グループ)
平成10年4月、福島市大原医療センター消化器科赴任
平成11年4月、東北大学医学部第三内科 消化器内科)医員
平成12年10月、東北大学医学部総合診療部 助手
平成19年4月、東北大学病院総合診療部 講師、医局長、副部長
平成22年3月、東北大学医学部教室員会 委員長平成23年6月、長崎医院 院長
院長 長崎裕
(略歴)
平成3年3月、東北大学医学部卒業
平成v3年6月、山形市立病院済生館 内科研修医
平成5年4月、東北大学医学部第三内科入局(膵グループ)
平成10年4月、福島市大原医療センター消化器科赴任
平成11年4月、東北大学医学部第三内科 消化器内科)医員
平成12年10月、東北大学医学部総合診療部 助手
平成19年4月、東北大学病院総合診療部 講師、医局長、副部長
平成22年3月、東北大学医学部教室員会 委員長平成23年6月、長崎医院 院長

 お問い合わせ
お問い合わせ

